本質に忠実なコンサルティング
深く・広く・正しく考える
出る杭の杜のコンサルティングの特徴
- 本質思考(偶有性に惑わされない)
- 目的意識(業務のための業務、プロジェクトのためのプロジェクトにしない)
- 顧客の顧客目線(顧客の自己満足で終わらせない)
戦略
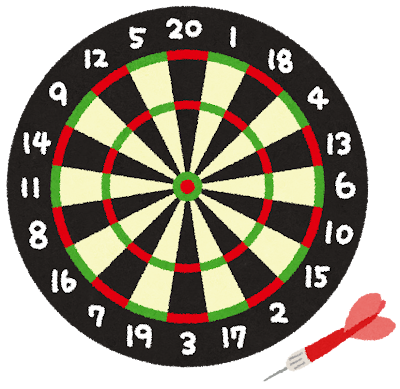
- ビジョン/理念/パーパスの策定
- 中長期経営計画の策定
- 年度事業計画の策定
- 業績評価指標の策定
- アウトソーシング戦略の立案
- 意識改革
- 業務領域ごとの各種事業戦略策定
業務革新(BPR:Business Process Re-engineering)

- SCM革新
- 設計革新
- 調達革新
- 生産管理革新
- 物流革新
- 販売革新
- 営業革新
- 経営管理革新
- 人事管理革新
DX(Digital Transformation)
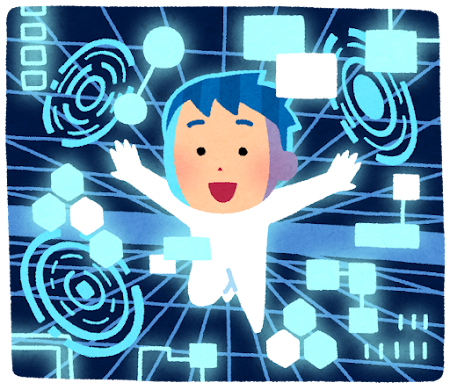
- DX化戦略の立案
- DX化のROI(費用対効果)可視化
- 各種DX化プロジェクト計画の策定
- 各種DX化プロジェクト計画の実行
イノベーション

- 革新的な商品の企画
- 革新的な組織の構築
- 革新的なビジネスモデルの構築
- 既存技術の多用途化
実績

費用(大手コンサル会社クラスのサービスを半額でご提供)
プロジェクト型 1カ月あたり(フルタイムの場合)※日単位もOK
グローバルBig4(目安)
- パートナー(VP):900万円
- ディレクター:700万円
- シニアマネジャー:500万円
- マネジャー:400万円
- シニアコンサルタント:300万円
- コンサルタント:200万円
出る杭の杜
- パートナー(VP):450万円
- ディレクター:350万円
- シニアマネジャー:250万円
- マネジャー:200万円
- シニアコンサルタント:N/A
- コンサルタント:N/A
スポット型 1時間あたり
グローバルBig4(目安)
出る杭の杜
※基本的に大手コンサル会社は
スポットコンサルを実施しません
- パートナー(VP):9万円
- ディレクター:7万円
- シニアマネジャー:5万円
- マネジャー:4万円
- シニアコンサルタント:N/A
- コンサルタント:N/A